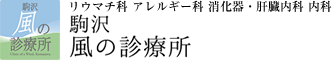B型肝炎
2021-05-27
B型肝炎ウィルスは、C型とは異なり、細胞の大切な核の部分までウィルスが侵入し住み込んでしまう為に、ウィルスを完全に排除できる治療は確立されておらず、活発なウィルスを活動しないように抑え込む、つまり“寝かしつける”治療が主軸です。核酸アナログという薬で、通常は内服がスタートするとのみ続ける必要があります。治療の適応に関しては肝臓専門医の適切な判断に委ねられています。また、35歳未満の方は、インターフェロンの治療により肝機能の長期改善効果が望め、薬剤中止後も抗ウイルス効果が持続するため、インターフェロン治療が選択されるケースもあります。
一方で、B型肝炎に感染していても、肝障害がない状態(いわゆる“キャリア”の状態)においても、6か月から1年程度の間隔でB型肝炎ウィルスの活動度を採血や超音波、Fibroscanなどで経過フォローする必要があります。
抗がん剤治療や免疫抑制剤やステロイドの長期投与を行う場合に、眠っていたB型肝炎が突然目覚めて活動することがあります。再活性化といわれていますが、その予防のためには、こうした治療が始まった段階から3か月おきにB型肝炎の活動度をモニターし、活動がみられる場合は速やかに核酸アナログをスタートする必要があります。抗がん剤治療や免疫抑制剤、ステロイドを使用しているケースでは、是非一度ご相談ください。
一方で、B型肝炎に感染していても、肝障害がない状態(いわゆる“キャリア”の状態)においても、6か月から1年程度の間隔でB型肝炎ウィルスの活動度を採血や超音波、Fibroscanなどで経過フォローする必要があります。
抗がん剤治療や免疫抑制剤やステロイドの長期投与を行う場合に、眠っていたB型肝炎が突然目覚めて活動することがあります。再活性化といわれていますが、その予防のためには、こうした治療が始まった段階から3か月おきにB型肝炎の活動度をモニターし、活動がみられる場合は速やかに核酸アナログをスタートする必要があります。抗がん剤治療や免疫抑制剤、ステロイドを使用しているケースでは、是非一度ご相談ください。