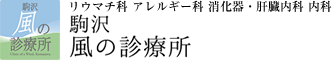アルコール性肝疾患
2021-05-27
我が国のアルコール消費量が頭打ちしているにもかかわらず、問題飲酒者の数は増え続けています。アルコールに端を発する肝炎、膵炎、消化管出血をはじめとした身体疾患、依存症などの精神疾患、本人の健康障害に限らず家族への深刻な影響や、アルコール飲酒運転などの社会問題など、アルコール健康障害対策基本法の制定後より国をあげて、不適切な飲酒を予防する方向性にあります。しかし、医療現場では、こういた疾患群に対する受け入れ態勢が不十分で体制化されていません。担当医師やコメディカル一人が、誠意を持って対応したにも関わらず、患者さんが抱える社会背景が大きすぎたり、アルコール離脱せん妄で管理が難しくなるケースも多いのが事実です。前勤務先である東京医療センターでは、精神科やソーシャルワーカーなどの多職種でチーム医療としてアルコール患者さんを受け入れる体制作りをしました。
一方で、アルコール性肝疾患(alcohol-liver disease:ALD)は、昨今、欧米から“アルコール関連肝疾患(alcohol-related liver disease:ARLD)としてこの病態が再定義される動きがあります。従来アルコール飲酒量エタノールにして男性60g/日(日本酒換算3合)、女性40g/日(2合)以上で肝障害を示唆する所見がある場合をALDと考えていましたが、男性30g/日(1.5合)、女性20g/日(1合)以上といった少ない量でも肝障害が示唆された場合ARLDとして疾患介入していく点にあります。この動きはまた、従来の禁酒治療以外に、まずアルコールを減らすといった”節酒”も治療の一端として考慮すべきというアプローチに基づくものと考えられています。
こうした現状を踏まえて、私自身が慶應義塾大学消化器内科アルコールグループに所属し研究してきた経験を活かし、当クリニックで果たすべく役割を考え、クリニックで介入できる範囲内において積極的に治療して参ります。また必要があれば、東京医療センターのアルコールリハビリテーションプログラム(Tokyo Medical Center Alcoholic Program with Physicians:TAPPY)や久里浜アルコール症センターとの連携も考慮していきます。
一方で、アルコール性肝疾患(alcohol-liver disease:ALD)は、昨今、欧米から“アルコール関連肝疾患(alcohol-related liver disease:ARLD)としてこの病態が再定義される動きがあります。従来アルコール飲酒量エタノールにして男性60g/日(日本酒換算3合)、女性40g/日(2合)以上で肝障害を示唆する所見がある場合をALDと考えていましたが、男性30g/日(1.5合)、女性20g/日(1合)以上といった少ない量でも肝障害が示唆された場合ARLDとして疾患介入していく点にあります。この動きはまた、従来の禁酒治療以外に、まずアルコールを減らすといった”節酒”も治療の一端として考慮すべきというアプローチに基づくものと考えられています。
こうした現状を踏まえて、私自身が慶應義塾大学消化器内科アルコールグループに所属し研究してきた経験を活かし、当クリニックで果たすべく役割を考え、クリニックで介入できる範囲内において積極的に治療して参ります。また必要があれば、東京医療センターのアルコールリハビリテーションプログラム(Tokyo Medical Center Alcoholic Program with Physicians:TAPPY)や久里浜アルコール症センターとの連携も考慮していきます。